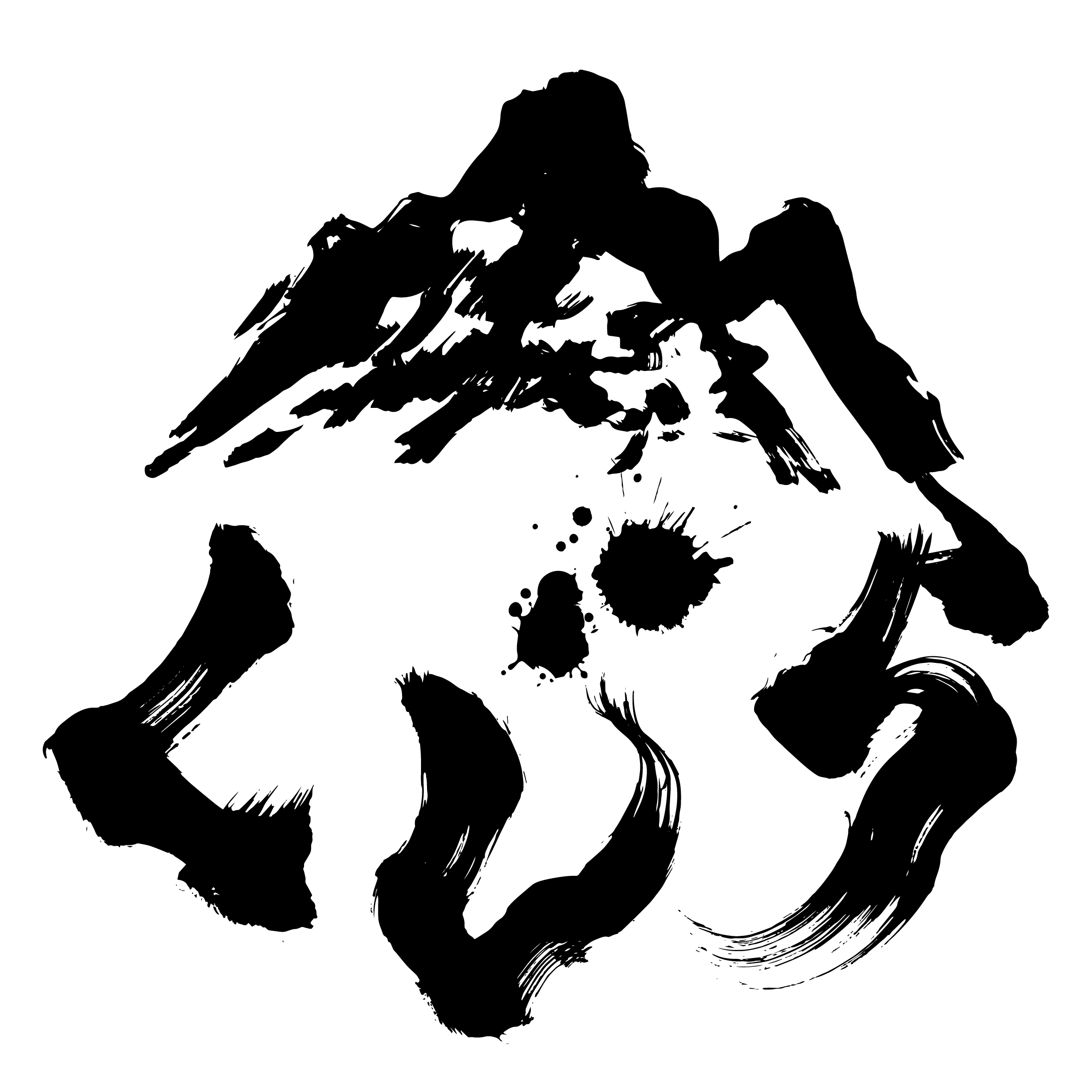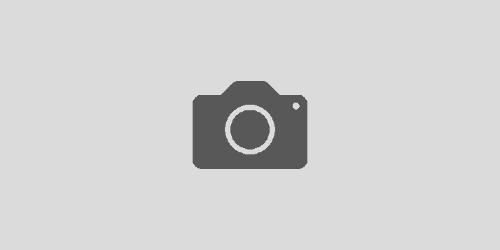書評『黄色い牙』エンタメ性が高く、風刺も効いている小説でした
狩猟系の本、特にマタギに関わる本は見かけたらできるだけ読むようにしています。
最近読んだのは『黄色い牙』。書いたのは志茂田景樹氏。直木賞受賞作ということで、注目度の高い1冊なのですが、お恥ずかしい話、この本の存在を知ったのは最近のこと。
とってもおもしろかったので、マタギ・狩猟系の小説に興味がある人はぜひ読んでみてください。
出会いは秋田犬阿仁町でした
電子書籍でも単行本でも読めます。電子書籍だとお値打ちですし、オススメですよ。
さて、この本に出会ったのは本屋さんでも、Amazonでもなく、秋田県阿仁町にあるマタギ資料館でした。
少し前ですが、マタギ文化をより近くで見てみたくて、マタギの里と言われる秋田県阿仁町に行ってきました。そのときの様子はいろいろキジにしましたので興味がある方はどうぞ。
▶秋田の旅土産話:マタギに興味を持った理由 ヒマラヤ山脈とマタギ
このとき訪ねた場所のひとつがマタギ資料館です。
マタギ資料館ではマタギが使っていた道具の数々や、マタギが作った毛皮やクマノイといったものを展示されており、普段は本でしか見ることができない貴重な品々を見ることができます。その展示物のひとつが、今日ご紹介する『黄色い牙』の直筆原稿でした。
直木賞を受賞したマタギ小説と言うことで、「コレは読まなきゃ」と思い手に取った次第です。
あらすじ
Amazonの概要はこのようになっています。
近代化の波に洗われるマタギ社会のゆるやかな崩壊を、そのリーダーである主人公の波乱の人生を通して冷徹に描く。直木賞受賞作。96年刊の改訂版。
非常に短いあらすじですが、まさにこの通り。時代は大正から昭和へと移り変わる時期。マタギで生計を立てることができた時代から、それじゃ食えない時代へと変化する微妙な時代でした。阿仁町も鉱山として発達し始めており、「マタギをやるより、鉱山で働いた方が稼げる」という考えを持つ人が増え始めました。さらに町はどんどん発展し、マタギがいた山村との差が広がっていった時代でもあります。
そんな時代に若くしてシカリを任された継憲が主人公。
毛皮をまとい昔ながらの伝統的な服装で猟に出たいマタギと、もっと現代的な服装、現代的な銃で猟に出たいと思うマタギが対立します。もちろんシカリである継憲は伝統的なマタギの姿を残したいと願っている。しかし、ただでさえ鉱山に人をとられ、マタギが減ってきているのに堅いことばかり言っては減少に拍車がかかる。
さらに困ったことに、伝統的なマタギを馬鹿にする勢力のリーダーである辰吉は継憲と同年代で、「我こそが本当はシカリになるべき」という思いがあり、事あるごとに突っかかってくる。思い通りにいかない辰吉はぐれて、犯罪に手を染め、悪い連中とつるむようになり、警察から追われる身に……。
この辰吉と継憲のぶつかり合いがこの作品の主題です。
波瀾万丈、ドキドキ……
決してつまらない記録小説のような作品ではありません。
実のところ、かなりエンタメ性が高くて、三角関係あり、熱い狩猟シーンあり、愛情のもつれからくる恨みつらみあり、時代の流れに抗えない絶望感あり、父を殺した犯人に関するミステリー要素あり(これは簡単に犯人はわかるのですが……)、うまくいかない子育てあり、とにかく最初から最後までドキドキワクワクの波瀾万丈の物語です。
理想と現実の間に挟まれ、「マタギとはこうあるべきだ!」という熱い理念と、近代化の波。時代を象徴するような風刺的なおもしろさと、そんなもの吹き飛ばすようなエンタメ性が交錯する作品です。さすが直木賞作品という感じ。
(一般に芥川賞は純文学といって、おもしろさより人間の内面を深掘りする作品が多い傾向があり、直木賞はもっとエンタメ性が高い作品が多いと言います。あくまで傾向で、簡単に区別できるものではないのですが……)
個人的には「直木賞作品は外さない」というイメージがあり、この『黄色い牙』も例外ではありません。確実にオススメできる1冊かと。
また、おもしろいと思ったらこちらをクリックしていただけると、ランキングが上がります。応援のつもりでお願いします。
ブログ村へ