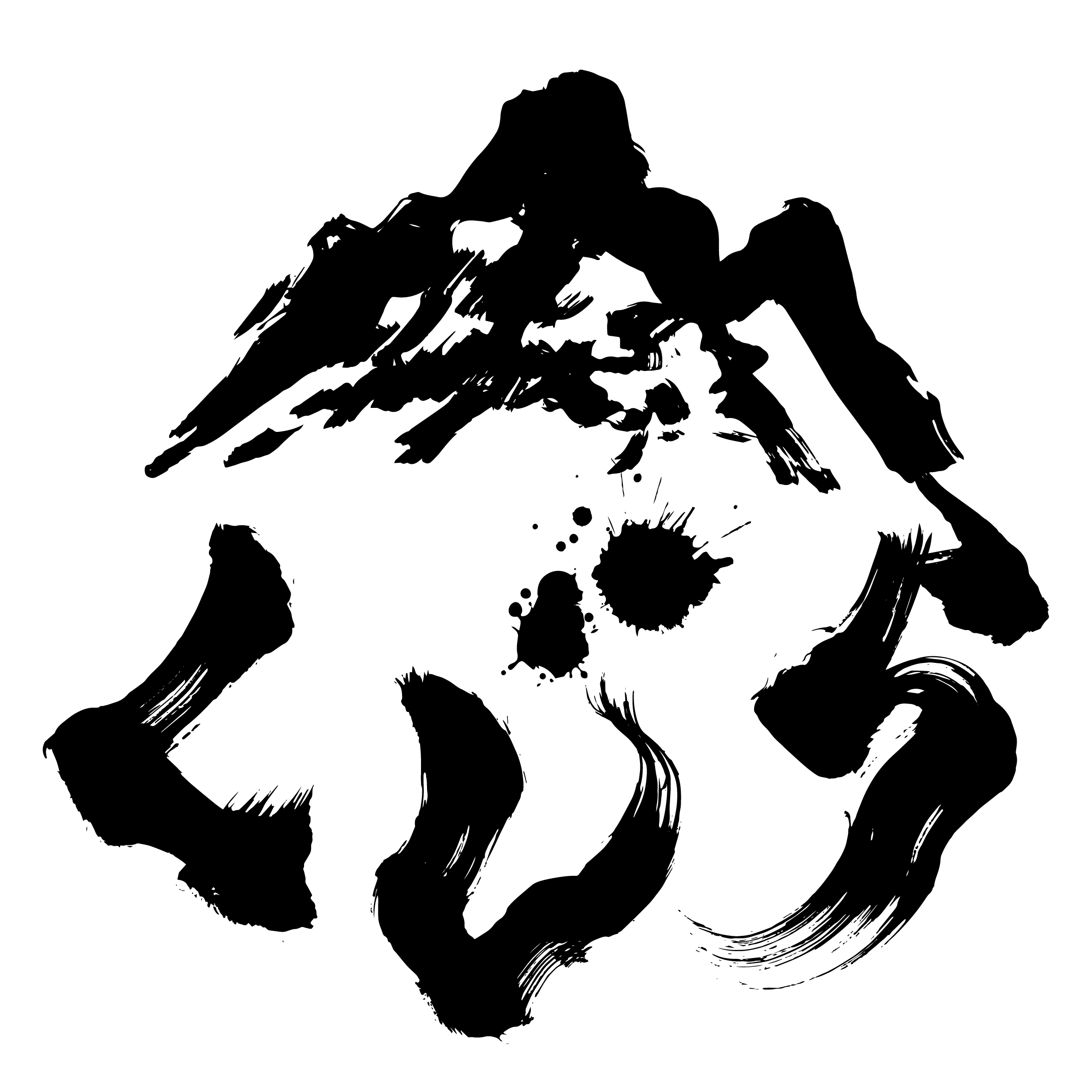前シーズンから使い始めた “関刃物鍛冶” さんのナガサと、自作のサヤを紹介します
新しくナガサを注文しました。それが “関刃物鍛冶” さんのナガサです。
まず自分なりに理想を思い描き、それを実現してくれる鍛冶屋さんを探そうと考えていたんですが、関刃物鍛冶さんのナガサを見たところ、「なんかこれそのまんま欲しかった形じゃないか!?」と思ってしまい、1点だけ要望をお願いした以外は、“関刃物鍛冶” 流のナガサに仕上がっています。
今日は自分なりにその理想をお話しするのと共に、その使用感や、自作のサヤもご紹介したいと思います。

これまでのナガサのミスマッチ

ぼくはもともと6寸の叉鬼山刀を使っていました。フクロナガサではなく、木の柄ナガサですね。
これはこれで気に入っていたし、あれこれ文句を言う気はありません。しかし、わたしのやることが少しずつ変わっていって、道具に求めることも少しずつ変わった結果、ややミスマッチを感じていました。
【刃の形状】
まず刃の形状です。叉鬼山刀系の角張った腹の形(と言えば伝わるかな?)にやや使いづらさを感じたのが発端でした。
刃先から、刃元までの連続性がないように感じます。たとえば皮剥に使おうにも、ちょっと使いづらく感じました。もちろん、解体は解体用の刃物を持っているので、ナガサでやる必要はないのですが、解体だけではなく、だいたいいかなる作業でも、この連続性のなさで小さなストレスを感じました。
【刃高】
叉鬼山刀はわりと刃高があるんですよね。血抜きなど、「突き刺す」という点においては、刃高が低い(つまり細い刃物の)方が刺さりがいいんです。
【6寸という長さ】
6寸を選んだのは私です。当時はそれで良かったのですが、昨シーズンに7泊ほど山に泊まって狩猟に没頭する機会がありました。
そういう野営が続くようになると、サクッと木を払い、必要に応じて薪を作るのに、6寸だとナタとしての性能に不足を感じるようになりました。
細かいことを言えば他にもありますが、概ねこの辺りに疑問を持ち始めたのが発端でした。
※誤解しないで欲しいのは、これはこの叉鬼山刀への否定ではないということです。自分なりに気に入って使っていましたから。でも「もしかしたら、自分には違う形が合うんじゃないか?」と思ってしまったので、試さずにはいられなかった……というお話です。
次のナガサに求めたこと
当然、先述の不満をふまえて、求めたのは
- 刃先から刃元まで連続性のある形
- 刃高の低さ(突き刺しやすい)
- 7寸で、できれば軽めに
という形でした。それをふまえて、ナガサの形についてあれこれ調べたんです。実際、ナガサの情報量が限られていて、その全貌を把握するのは難しいんですが、参考になったのはこちらのブログ記事でした——
この中で秋田のナガサの中でもいろんな種類がある事がわかりました。タシロ型、五城目型、秋田型、今知られている秋田型(叉鬼山刀系)と分類されていることが分かります。リンク先に手書きの形状の違いを示す図があるので、ぜひご覧になって欲しいです。すばらしい資料です。
とっても分かりやすい分類になっていて、ぼくの目線で見ると——
- 突き刺しに特化した五城目型
- 突き刺しを捨て、腹の丸みを強調したタシロ型
- その間の「いわゆる一般的な秋田ナガサ」
自分の中で思い描いていた形状はまさに3つ目の「いわゆる一般的な秋田ナガサ」でした。
それを “関刃物鍛冶” さんが作っているということを探り当て、無理を承知でメールで注文したのです。
できあがったナガサはこちら
注文するにあたり、お願いしたのは「毎日のように持ち歩くものだから、軽くしたい。少し薄くしてしまってほしい」ということです。
それに対して「うちのナガサは一般的なものに比べて裏すきが深いので、もともと少し軽めだし、さらに薄くしてもそれほど軽量化にはならないよ」とのことで、それならば「もう関刃物鍛冶さんの基本のナガサ(7寸)をお願いします」と依頼しました。
で、できあがったのはこちら——

気持ち薄めに作って頂いたとのことでした。
もう大満足ですよ。まだ1シーズンの利用で、酷使したとは言いがたいですが「来期もこれでいく」と断言できるのは確かです。
ナガサをもつ理由を改めて——
ずいぶん昔にナガサを持つ理由について書いたことがあります。
読み返してみて、いまも感覚は変わらないですね。ただ、ちょっと変わってきたのは、昨シーズンにヒグマを探すべく、山に1週間ほどこもった経験から、短時間で寝場所を作るのにやっぱりナガサ(剣ナタ)は無理がきくな〜ってことです。
寒いので、たっぷりと薪を手配したり、一晩を過ごすのに必要なものを用意したりするのに便利です。もちろんないならないでいいんでしょうけどね。ヒグマを探して山に泊まるので、夜の護身用(というかお守り)に枕元に置いてましたが、やっぱり心強いです(ヒグマに勝てるとは言ってない)。
自作のサヤ


正直に言うと、サヤは自分で作るのが1番かな、と思います。使い方によって、あるいは好みによって、求めるものが違うでしょうからね。自分が上手に作れるという意味ではないんですが、ぼくは自分が作った物が好きです。
ぼくなりに意識したのは薄さです。厚ぼったいとどうしても存在感が強くなるので、薄ければ薄いほどいいな、と。
もちろんやり過ぎれば強度の問題が出るので、バランスは大事ですけどね。サヤは刃物を入れる容器ではあるんだけど、じつは決して脇役ではなくて、サヤの使い勝手で、ナガサ・剣ナタ全体の使い勝手が変わるほどのインパクトがあると思っています。
関刃物鍛冶さん、すごく良かったけど、対面販売が基本です。
関刃物鍛冶さんを紹介するに当たり、一応強調しておきたいのは「対面販売が基本」ということです。

わたしはメールでやりとりして作って頂きましたが、いつも受けているわけでもなさそうです。ホームページはないと思うんですが、YouTubeは熱心です。そちらのコミュニティを見てもらうと、ネット販売しているかどうか、書いてくれています。
https://www.youtube.com/user/TheKaziyasann/community
2022/06/11の時点では「一部製品のみ」受注再開というコメントがありました。
一部の品物について注文の受付を再開させていただきます。
今後しばらくの間、注文を受け付ける品物は以下の通りです。
・鎌類各種、鍬類各種、片手斧、6寸以下のナガサ類 以上。
これ以外の品物は、材料や資材の入荷に目途が立たない物が有りますのでお受けできません。
特に、6寸以上のナガサおよび角鉈類に使用しております柄の入荷時期は現在未定です。
誠に申し訳ございませんが、現在在庫している小さい柄で対応できる刃渡りのみ受注いたします。
※本日よりお受けした注文は最短の納期が6月末頃~になりますのでご了承ください。
※ご不明な点はこのチャンネルの概要欄ご参照のうえお問い合わせください。
先方の状況をふまえてご注文するようにしたいですね。
また、おもしろいと思ったらこちらをクリックしていただけると、ランキングが上がります。応援のつもりでお願いします。
ブログ村へ