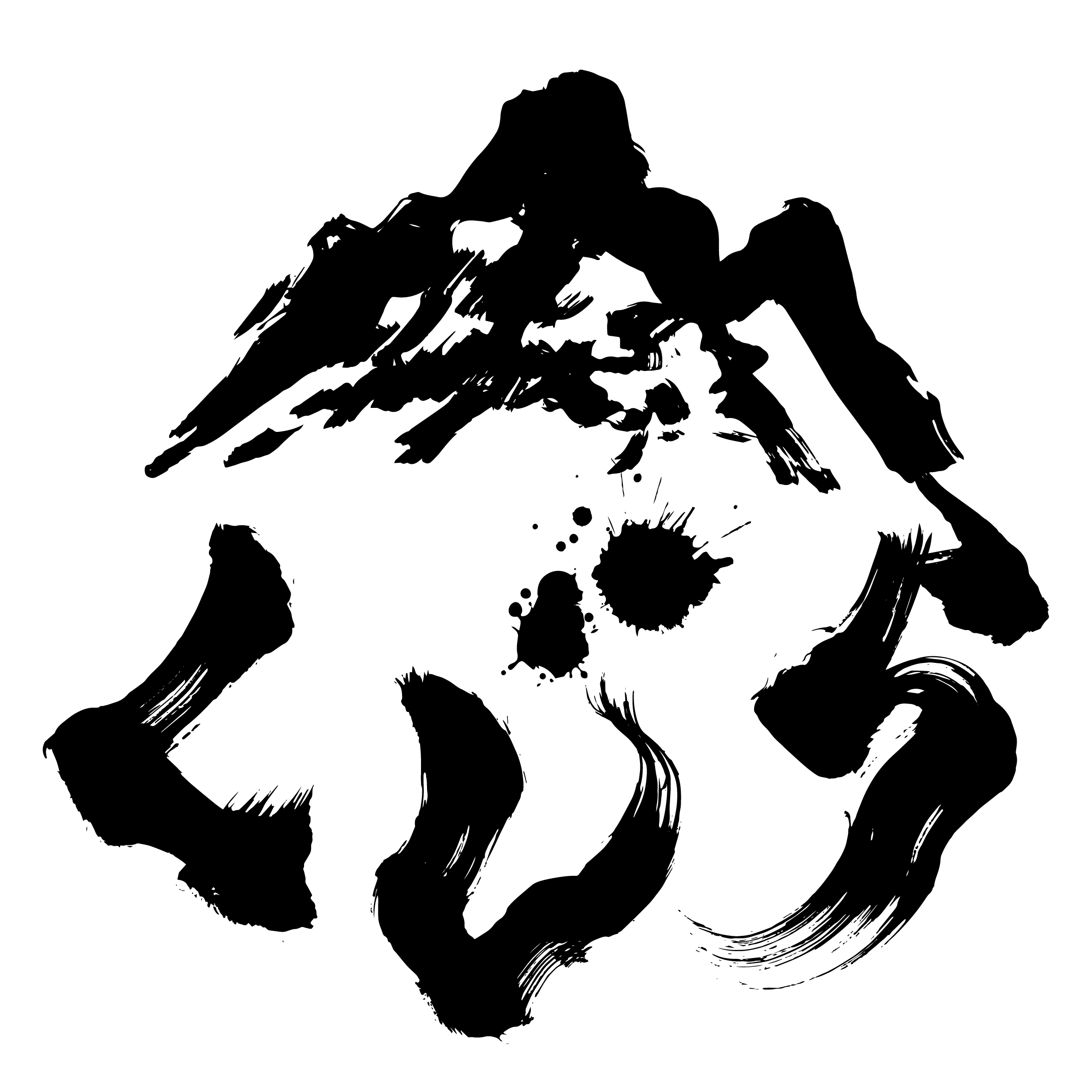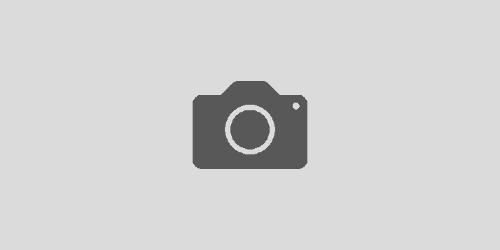【軽量化】水は現地で作れば軽くなる【考え方】
山において、軽量化ってのは延々とつきまとう問題です。
今日は長期山行では常識だけど、日帰り山行だと忘れがちな「水の軽量化」について書いてみます。
動画版
水は重い

水は1リットルで1kgです。あたりまえですね。
さて、日帰りで山を歩くとき、水をどれくらい持っていきますか? 日本山岳ガイド協会の計算式を拝借すると——
吸水量(飲む量) = 脱水量(汗) × 0.70~0.80
脱水量 = 体重(kg)× 行動時間(h)× 5(ml)
登山に必要な水の量と汗のはなし
となるらしいです。実際に計算してみましょう。ぼくは体重が72kgくらいですので、行動時間を8時間として——
脱水量 = 72 × 8 × 5 = 2,880ml
給水量 = 2,880ml × 0.7 = 2,016ml
というわけで、だいたい2リットルの水が必要らしいです。
これはもちろん登山における計算でしょうから、忍び猟で、もっとゆっくり行動すること、そして立ち止まる時間も長かったりすること、急勾配ばかり登ったりしないことを考えればこれよりも少なくても問題ありません。行く山によっても変わるでしょうね。
まぁ、ぼくは経験上、1リットルあれば十分なことが多いです。それも余らせて下山することも少ないありません。
念のため・予備の水
さて、水に関してはギリギリを攻めることはあまり良い習慣ではありません。
ちょっとした道迷い。想定外の疲労、発汗、体調不良などに対応できないからですね。ぼくはわりと心配性なので500mlくらいは余計に持っていきたいと考えて、結局は1.5リットルくらい用意するんです。
でもね、毎回毎回500ml強は残して下山します。0.5kgですよ。多いときだと0.7kg分くらい残してます。
500〜700gって大きいですよ。いろんな道具に金をかけ、あるいは工夫を重ね、50g100gと軽量化しているというのに、「念のため・予備のため」と背負う水が500〜700gって残酷な重さです。
長期山行ではどうしてるんだっけ?

さて、日帰り山行ばかりやっていると、つい考え方が日帰りの考え方になってしまいます。
でも高所登山・縦走・極地探検のような長期のアウトドアでは水をどうしているんでしたっけ?
水は現地調達が当たり前。沢の水を沸かす。雪を溶かす。そういった方法で飲み水を作ります。
日帰りだってそれでいいじゃん
 となれば、日帰りの山行だって、水は現地調達することを考えても良いんじゃないかな、というのがぼくの考えです。
となれば、日帰りの山行だって、水は現地調達することを考えても良いんじゃないかな、というのがぼくの考えです。
たとえば500mlくらいの最小限の水は背負った上で、水が近いところで休憩するときは水を沸かして飲む。雪を溶かして飲む。そんなゆとりがあっても良いかな、って。
そうなると沸かすための燃料が必要になります。ガス・ガソリン・アルコールなどいろいろあります。そのあたりは好みでいいでしょう。500mlの水は携行し、追加で必要となる1リットル分くらいの水を沸かす燃料を携行すれば、かなりの軽量化になります。
どれくらいの燃料で、どれくらいの水を沸かせるか? これは使うストーブ、燃料、気候などによりますので、自分で確かめましょう。こういうのが経験値というヤツです。
焚火台の強みがここで

ぼくは焚火台を活用することも多いです。
昼食の料理に焚火台を使う前提で行動するならば、水もそこで沸かせば良いんです。焚火台は200g未満。これで1リットルでも2リットルでも沸かせます。
これが焚火台の強みです。飯を作っている横でタップリと水を沸かせばいい。ガスストーブなんかだと1つずつしか調理ができませんが、この焚火台なら平行して複数の調理ができます。炊飯しながら水を沸かせる。燃料は現地調達で0g。
どうせ昼食のために焚火台とコッヘルを持って行くのだと考えれば、追加容量なしで水は作り放題です。
たとえば「500mlの水を携行し、昼の休憩時に飯を作る横で500mlの水を沸かして、下山時の水分とする」何てことが可能です。
これで、背負う水の量をグッと減らせるというわけです。
アルコールストーブもいい


アルコールストーブは火力としてそんなに強いものではありませんが、最近では構造的な工夫でかなり改善されています。
1リットルとかではなく、その場で飲む150〜300ml程度ならストレスなく沸かせます。1日の山行で2〜3回の休憩をとり、そこで毎回200mlのお茶なんかを沸かして飲めば、それだけで600mlの水分量。
小刻みに水を作ることで、もっていく水の量を減らすことも可能です。
そもそもの前提として
ここまで書いたのが机上の空論というか、理想論です。
実際の山行ではこれらを踏まえ、現地の様子を考える必要があります。
- 水場はあるか?沢、池、雪
- 沸かす時間的余裕はあるか?
- 焚火に依存するなら天候は? 焚火はできる場所か?
- 怪我をしたとき、熱射病などで水が必要になったらどうするか?
などなど、気にするべきことはあります。これらは「経験値」です。自分で考え、水を背負わない代わりに、背負うリスクのことを考える必要があります。
発想として、自由になるために

水を現地調達するっていう考え方は長期山行なら常識です。
でも日帰りでも、その発想は活かせます。ぼくが行く山でも、水場は把握しているので「あそこで休憩して沸かそうかな〜それなら300mlは減らしてもOK」みたいにザクザクと計算し、減らしていきます。
軽量すればもっと歩けます。もっと遠くまで、もっと早く、もっと気持ちよく取り組めます。
こういうやりかたもあるよね、と頭の片隅に入れておくだけでも、自由度が上がるよね、というお話です。
また、おもしろいと思ったらこちらをクリックしていただけると、ランキングが上がります。応援のつもりでお願いします。
ブログ村へ