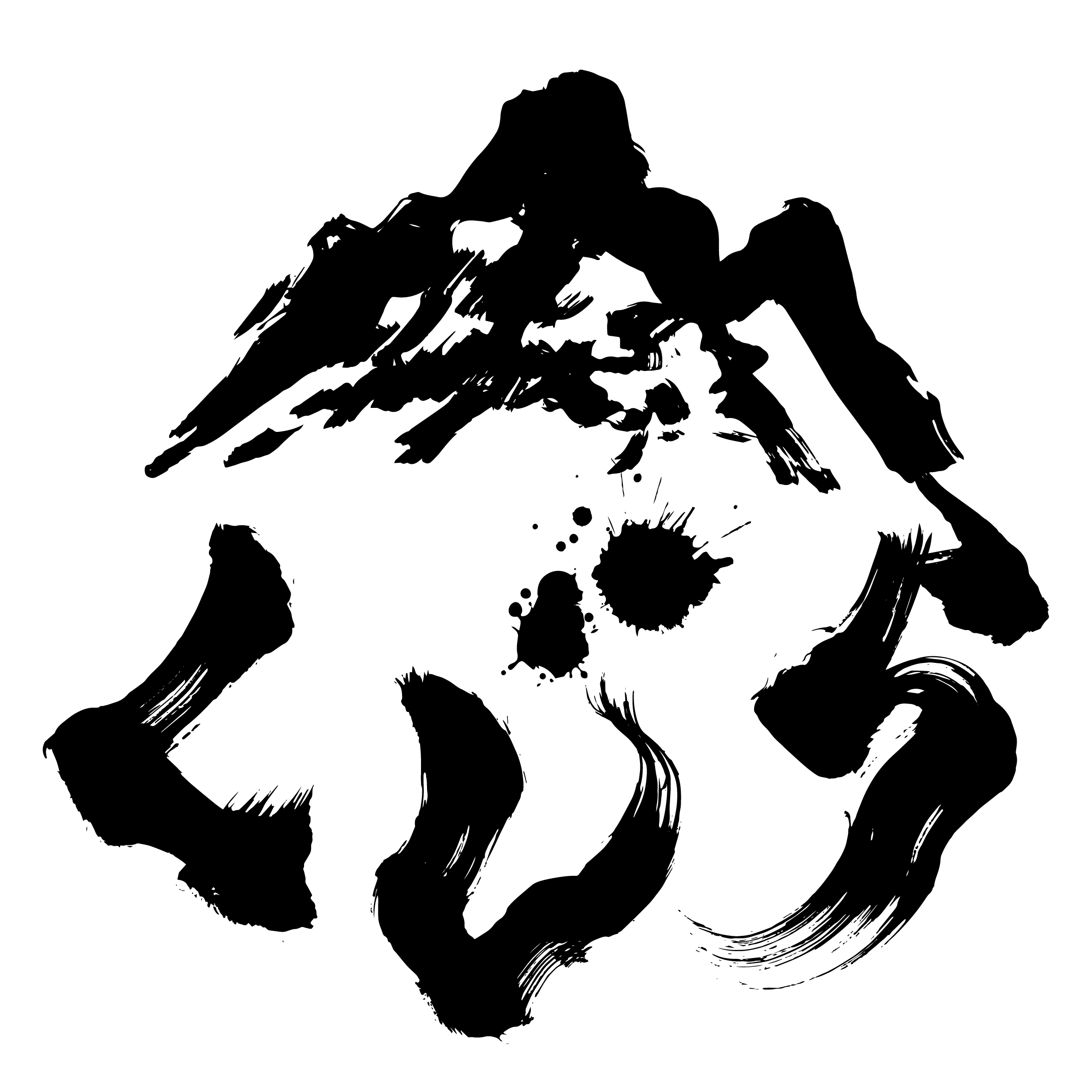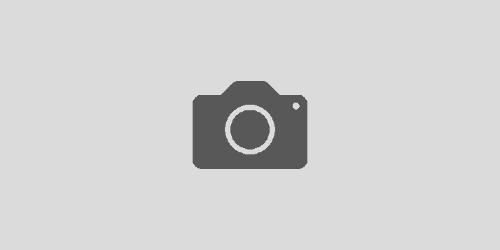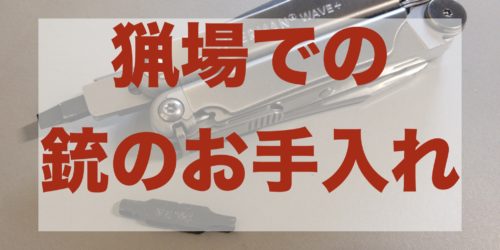【2-5-3システム】単独忍び猟での弾の携帯方法【安全性と利便性】
単独忍び猟での弾の持ち運び方については、いろいろ悩んで考えてきました。
いろいろ納得してみたり、また不満が出て変更してみたり……。
で、現在は自分で『2-5-3システム』と呼ぶ形に収まっています。ぼくなりに考えてやっていることなので、その思想やメリットなどをまとめてみたいと思います。
動画版もあるよ
持ち運ぶ弾の数は?
山に持っていく弾の数についてはこちらの動画でお話したことがあります。
結論を言えば6〜10発なんですが、最近は基本的に10発です。その理由は動画の方をご覧ください。
弾差しの持つ機能

さて、弾の持ち運び方に入る前に整理しておきたいのが、弾差し(ショットシェルホルダー)に求められる機能について。
ぼくは2つの機能に集約されると思っています。
安全性: 弾をなくさず管理し、ひと目で数の確認ができること。
利便性: 必要なときに、素早くスムーズに必要な弾を取り出せること
ご想像の通り、この2つの機能は相反するもので、一方を高めていくと、もう一方が犠牲になっていきます。結局は『バランス』ってことですね。安全性を担保しつつ、利便性も確保して……。
そのバランスを僕なりの方法で取っているのが、これから説明する『2-5-3システム』です。
2−5−3システム
結論ですが、ぼくは弾を3つに分けて収納しています。
2発:X-Holder——開放型の弾差しで、利便性最強(カカシラボ製)

5発:HSGI改——脱落防止カバーを自作し、安全性に振っているが、必要があれば素早くアクセス可能


3発:ウエストポーチの奥底にしまってある(安全性最強/利便性最低)
上に行くほど利便性が高く、下に行くほど安全性が高いという形になっています。
単独忍び猟だとバカスカと数を撃つことはありません。1日に1発も撃たないことも多いし、撃つとしても基本は1発。必要があれば止め撃ちにもう1発撃つ程度。だから即座にアクセスしたい弾は1〜2発なんです。
そこで最初の2発だけは利便性を重視しつつ、残りの7発は安全性を優先することで紛失事故の確率を下げる、というわけ。言うまでもなく、最初の2発も「利便性を重視しつつも、十分な安全性を担保しているんですけどね。
また、ウエストポーチに収納している最後の3発は予備であり、お守りです。その弾に手を伸ばすことがあれば、私の中では「なにかおかしい」とき。7発を撃ちきって、まだ撃ちたいことなんて想像できないので、その時点で猟は終わりですね。その3発で猟をすることはないです。たとえば「どうしても止め撃ちに使いたい」みたいな場面で使う程度。
実際の安全性以上に心の平穏が大事
さて、安全のためにこうやって管理しているわけですが、実際には「心の平穏」を大事にしたいためにやっているのが正直なところです。
というのも、狩猟で山を歩いているとき、ぼくは「弾を落としてないよね」と不安になっていつも確認してるんです。とくに開放型のホルダーだと。
その分だけ猟に集中できていないわけです。
そこで最初の2発以外のカバー付きポーチに入れちゃうことで、「あんまり気にしなくて良い」という状態にして、心の平穏を保っているっていう感じ。
弾の持ち運び方はみなさんいろいろ工夫しているでしょうから、「ぼくはこうしてるよ」ってのがあったら、ぜひTwitterとかで教えてくださいね〜。
また、おもしろいと思ったらこちらをクリックしていただけると、ランキングが上がります。応援のつもりでお願いします。
ブログ村へ