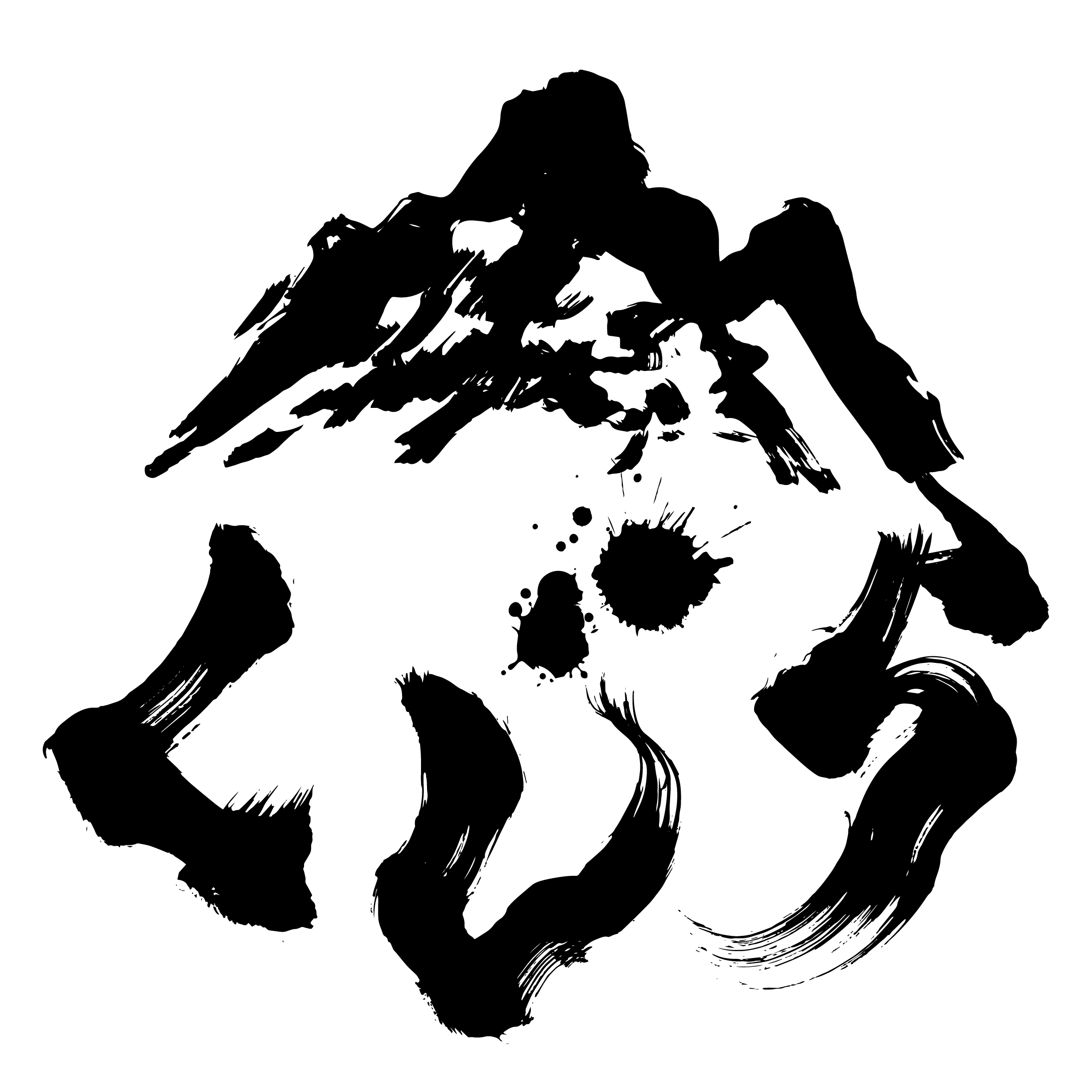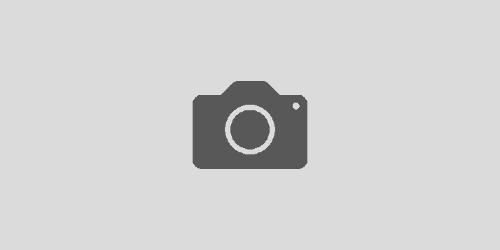雨の日にソロストーブを着火させた手順
先日、山に入った時に小雨が降ってしまいました。そうでなくても連日の雨で地面はぐっしょり、落ちている枝もみんな濡れている状況でした。
手持ちのストーブはソロストーブ1つ。
苦労しつつもちゃんと調理ができましたので、そのときの手順や工夫を記録しておきたいと思います。
多少の雨ならちゃんとソロストーブでもうまくいきますよ。
ちなみに写真は参考として後日撮影したものです。当日のものではないので、濡れてもいません。雰囲気が伝わればと思って撮影しました。
乾いたやや太めの枝探し
まずは燃料にする枝を探します。
ソロストーブでは、通常「爪楊枝くらいの枝」と「小指くらいの枝」を集めて着火しますが、それくらいの太さの枝は、みんな芯まで濡れており、着火に苦労しそうでした。
こういうときはむしろちょいと太めの枝を利用します。表面は濡れていても、中心部分は意外と乾いているものです。
指4本分ちょいの(ソロストーブにしては)太めの枝を集めました。
底に敷く枝を準備
まず集めた枝の濡れた表皮をナイフでザッと剥いじゃいます。これは全部やる必要はなく、最初に使う分だけ(全部やってもいいですが)。
そいつをバトニングして1/4サイズにします。

乾いた面が露出するので、そいつを短く折ってソロストーブの半分くらいまで敷き詰めます。
多少濡れていても木は乾きながら燃えますが、こうして乾いた面を露出させることで、早く引火させる作戦です。
小さなフェザースティックを作る

小指〜人差し指サイズの小さなフェザースティックを作ります。できればたくさん作ります。
着火材としてガムテープを使うので、薄いフェザースティックを作る必要はありません。粗くていいので、小さいのをたくさん作っておきました。
ガムテで着火
ソロストーブに丸めたガムテを入れて着火し、作っておいたフェザースティック乗せていきます。乾いた綿を露出させ、そこをフェザーにしたおかげで結構燃えます。

つぎの問題は上からの雨。
タープを持っていれば屋根を作ってしまうところですが、あいにく持ち合わせていないので、近くにあった白樺の倒木から皮を剥いできます。
もう完全に湿っていますが、その中でも比較的乾いた部分をソロストーブの上に乗せます。つまり樹皮を屋根にしてしまいます(適当に隙間が空くように)。
こうすることでソロストーブ内に熱がこもり、結果として中の着火も速く進みます。上からの雨も防げるし、そのうち乾けば白樺の樹皮も燃えていくので良いことづくめ。
ちゃんと着火したら上に鍋を置くので、もう雨はあまり気にしなくても大丈夫です。
ひたすら粗いフェザースティックを投入
普通の焚き火であれば、ある程度火がつけば、濡れた枝をどんどん投入しても問題ありません。強い火力によって乾き、燃えていきます。
しかしソロストーブは容器自体が小さく、火力を極端にあげることができません。
この小さな容器に濡れた枝を投入しても、すぐに燃えることはなく、しばらく経ってからやっと燃えるという感じ。
なかなか安定的に燃えないのです。火が強くなったところで次の枝を投入しても、持続せず、いったん火力が下がり、枝が乾いたところでパッと強くなる感じです。
そこでどうせ暇ですし、小さな粗いフェザースティックを作っては投入し続けました。
フェザースティックと言っていますが、まぁかなり粗いものです。


フェザー状になっているので、多少湿っていてもすぐに乾いて燃えていきます。火力も維持しやすく、うまくいきました。

まとめ

手順をまとめると
- 極力乾いた太めの枝を集める
- 枝を割って、乾いた面を露出させ、ソロストーブの底に敷く
- 小さいフェザースティックとガムテで着火
- 白樺の樹皮で雨よけ
- 火力維持のために粗いフェザースティックを投入し続ける
という感じですね。まぁ、乾いた環境なら火なんて簡単におこせるものですが、濡れてるとどうしても苦労しますね。頭の中には何度も「アルコールストーブを持って来ればよかった」という言葉が浮かんでは消えていきました。
もちろんそれでもいいのですが、こういう苦労をたまにしておくと自信が湧きますね。「雨でもやれる!」って。
(そして撮影用に晴れた日に着火したのですが、死ぬほど楽でビックリしました。最近、濡れた環境でばかりソロストーブを使っていたので、こんな条件がいい中で使うのは久しぶりでした笑)
また、おもしろいと思ったらこちらをクリックしていただけると、ランキングが上がります。応援のつもりでお願いします。
ブログ村へ