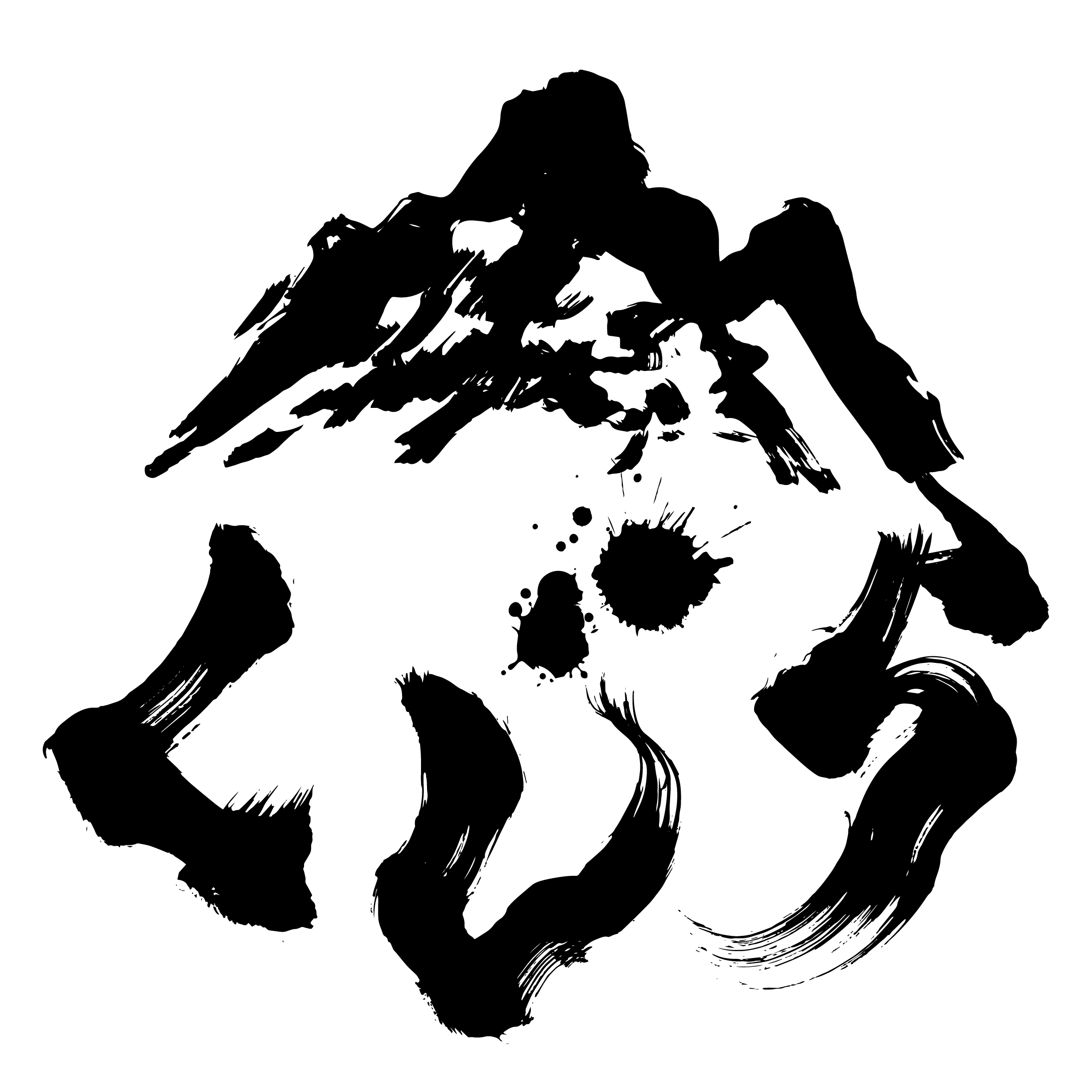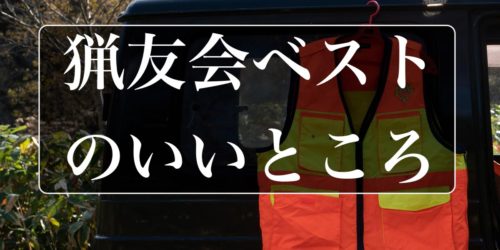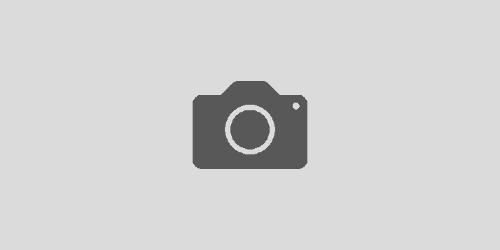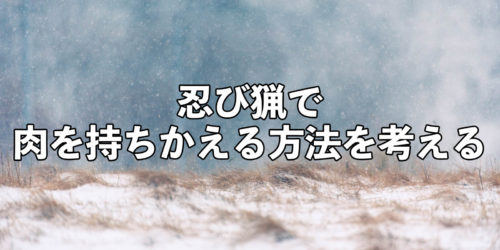アイヌ民族の背負い縄をヒントに肉の運搬を考える
単独猟で肉の運搬は大きなテーマです(という文をこれまで何度書いてきたことか……。いまだにまったく答えに辿り着いた気がしないのですよ……)。
で、少し歴史を紐解いて、先人たちはどうしていたのか考えてみるのも一興だろうとリサーチしてみたら、マタギやアイヌ民族の人たちが “背負い縄” と呼ばれるものを使用していることが分かりましたので、その形をヒントに考えてみることにしました。
背負い縄について検索してみる
まず、背負い縄というキーワードで検索してみると、アイヌ民族の資料に当たりました。
※リンク先に写真があります。
説明文を一部引用してみます。
「アイヌはこの背負い縄に荷物をしばりつけ、これを額にかけて背負います。そして山の中を歩くときは、突然熊に出会っても首をうしろへひと振りするだけで背中の荷物をうしろへ落とし、即座に身軽になれるように常に心がけていました。そうすれば、手に残った弓矢や槍で熊と戦うことも、身をひるがえして逃げることもできるわけです。これも常に危険と背中合わせの生活を営んでいた、狩猟民族であるアイヌの身を守るための一つの知恵です。
おもいしろいですね。アイヌは北海道(当時の蝦夷地)や本州北部の先住民族です。ヒグマの存在を意識せざるを得ない毎日だったはずです。だからこそ、このような工夫が必要だったのでしょう。
もちろん額にかけて荷物を運ぶのはアイヌの専売特許ではありません。東南アジアの国々でも普通に行われていることですし、ネパールのシェルパ族なども山での荷物の運搬はこの方法です。
さらに調べていくと、背負い縄にも先ほどご紹介した “頭かけ式” とはべつに “肩背負い” と呼ばれるタイプがあるようですね。
※リンク先に写真があります。
こちらは具体的にどのように荷物を縛り、肩に背負っていたのか完全にイメージはできていないものの、写真を見ればなんとなく想像はできます。
頭かけ式にせよ、肩背負い式にせよ、基本的な発想は「背負う部分は肩や額に優しい作りになっていて、あとはただの縄」ということ。つまり袋とかバッグの要素はありません。あくまで “背負い縄” なんですね。
このアイディアのよいところはとにかく荷物を軽量化できることでしょう。とりあえず、この背負い縄を1つ持っていれば、あとは現地で荷物を縛り付けて背負ってくれば良いのです。
また、縄という特性上、小さなものでも、大きなものでも、いびつな形のものでも、背負うことができます。最小限の荷物で、最大限に活用できるアイテムです。
アイディアは良いが、頭かけ式はきびしい
本当にシンプルなものなので、実現は簡単ですが、現実的には頭かけ式はきびしいと感じました。
先日、実際に肉を背負ったときにやってみたんです。
背負うのは楽でも、左右の揺れに弱い……。安定した林道やけもの道を歩くときは良いのですが、道なき道をグイグイ上るときなんかは身体がちょっと左右に揺れるだけで、背負った肉がグワングワンと揺れてバランスを崩します。
じゃぁ、肩掛け式か……となるわけですが、これは肩ひもが2つ必要で、ギリギリまで荷物を減らしたい私にはやや不満。できるなら肩ひも1つでも削りたいという気持ちです。
というわけで、頭かけ式と同様に背負い部分は1つにし、たすき掛けして背負うというのが私の今のところの結論です。
縛り方や背負い方に工夫が必要で、まだ模索が必要なのですが、少なくともそれなりの肉の量を背負って帰ることができたので、自分的にはよい可能性を感じています。
使った肩ひも
で、背負い縄の背負い部分に何を使うか?
amazonなんかを見ると、現代的なキャリーベルトというジャンルのアイテムがあるようです。
ちょっと大袈裟に見えますが、機能的には使えそうですね。こんなに大きなものを運ぶわけではないですが、ロープ部分を切って短くすれば使いやすいかもしれません。
——ただ、アイディアをアイヌ民族から持ってきたので、ちょっとそういう雰囲気のある道具を使いたいな〜と、変な色気が出てきてしまいました。
あったあった!

で、家の荷物を漁っていて出てきたのがこれです。
わたしがネパールに行ったときに、ヒマラヤ山脈の中にある小さな村で購入したものです。ヤクの毛で作られたカメラ用のストラップなんです。要するに土産品ですね。
じつは誰かへのお土産にしようと購入したんですが、特に誰にもあげないまま押し入れの奥底にしまってありました笑。
これは風情があるじゃないですか。
素材としても軽いし、丈夫だし、肩に優しいし、長さも手頃と言えば手頃。
いつもカラビナとスリング2本は携帯しているので、その組み合わせでいろいろできそうです。
カラビナはこんなのをいつも携帯しています。使い道は無限大。狩猟中は1つはベルトに下げて、ビニールテープをぶら下げています。なんかをちょっと補修したりするときに便利。獲物が獲れれば、肉を吊すのに使ったりします。また、ロープと組み合わせてガルダーヒッチなんかに使ったり、ちょっとした支点に使うことも。

こちらは肉を吊しているときの写真です。枝がなくても、幹に巻き付けてしまえば肉は落ちません。

でまぁ、カメラストラップにカラビナを付ければこの通り、背負い縄になるというわけです。

肉を袋に入れて、スリングで梱包して、カラビナを引っかけてやれば “頭かけ式” でもいけるし、“たすき掛け” でもいける。まだ研究はいりますが、最小限の荷物で肉の運搬をするという意味では、ひとつの答えに近づいた気がしました。
やっているうちに不満も出てくるだろうとは思うので、今後も模索していきたいと思います。
また、おもしろいと思ったらこちらをクリックしていただけると、ランキングが上がります。応援のつもりでお願いします。
ブログ村へ