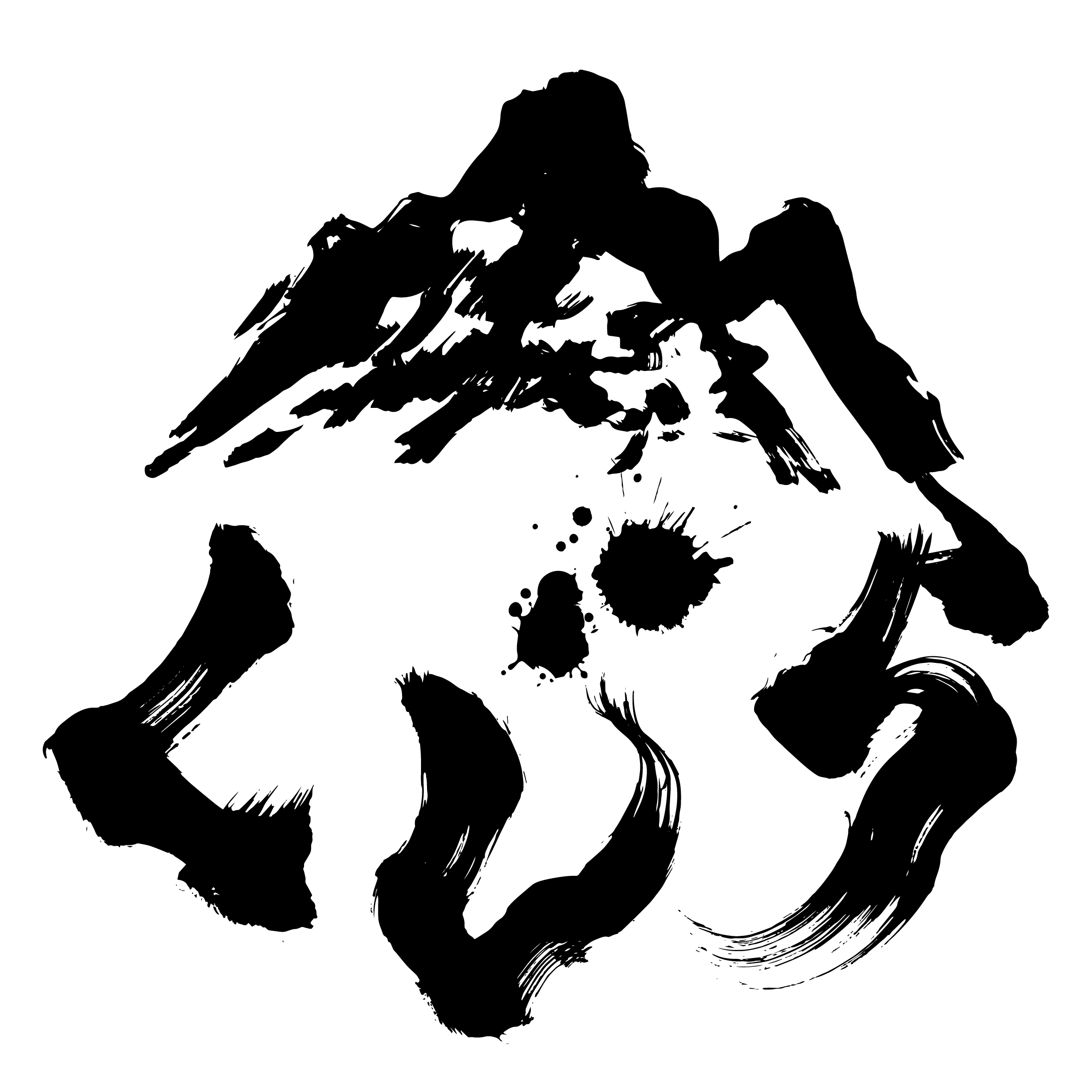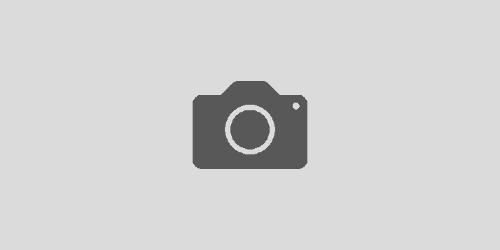狩猟免許6:狩猟免許試験の勉強で意識した5つのこと+おまけ1つ
さて、狩猟免許の試験に合格したので、偉そうに「勉強の仕方」について書いてみようと思います。
わたしなりに結構マジメに勉強しましたし、興味があることなので勉強自体は楽しかったです。
これから狩猟免許試験を受けるという人のために、わたしなりに気付いた「勉強のコツ」をシェアしたいと思います。
ほかにも「おれはこういう風に勉強した」という人がいればコメントで教えてください。
とにかく暗記
本題の「意識した5つのこと」に入る前に、ひとつお伝えしたいのは、「結局は暗記だぞ!」ということ。
体系的に理解することも大事ですが、最後は暗記です。繰り返し狩猟読本を読み、例題を解き、必要ならノートに何度も書いて暗記する。それが大事です。
これからご紹介するポイントは、わたしなりの暗記の方法であると言ってもいいと思います。
1. 例題だけに頼らない
猟友会の講習会に参加すると『狩猟読本』と『図解 狩猟免許試験例題集』の2冊の参考書をもらえます(参加しなくても購入できるようです。猟友会のサイトを参照してください)。
で、受講者の声を聞くと、「とにかく例題だけやった」という人もいるようですが、例題はあくまで例題です。
例題だけやりこんでも、ちょっと問題の形が変わったら解けなくなります。例題は「こういうポイントが問題になるんだな」という参考にとどめた方がいい、というのがわたしの意見です。
たとえば例題のなかで「キジやヤマドリには、3号前後の散弾を使用する」という選択肢があるのですが、これの正誤だけを覚えても仕方ないのは当然でしょう。キジ・ヤマドリは5~6号であることを覚えるのはもちろんですが、スラッグ・OOB・BB・1号~10号など、すべての弾丸の適用鳥獣を覚える必要があります。
例題を軸にして、周辺知識を広げましょう。
2.「鳥獣の知識」は体系的に理解
「鳥獣の知識」の章はかなりボリュームがあり、暗記も一筋縄ではいきません。とくに見慣れた動物はともかく、見慣れない(自分としては)注目したこともないような鳥獣の特徴を覚えるのは大変です。わたしはイタチとかヒドリガモとか、いまいちピンとこなかったですね。
で、どうするか? 体系的に覚えましょう。
たとえば「マガモは雌雄異色」「カルガモは雌雄同色」「コガモは雌雄異色」と1つずつ暗記すると大変です。なにしろ狩猟可能なカモだけでも11種。オスメスの違いだけでも11個の暗記事項があるわけです。
ここはドカッと「カモ科はすべて雌雄異色。例外はカルガモ」と覚えた方が簡単です。
ほかにも体系で覚えられるモノとしては——
- 「カモ科マガモ属は陸ガモ」
- 「カモ科ハジロ属・クロガモ属は海ガモ」
- 「キジ科は雌雄異色。例外はコジュケイ」
- 「スズメ目は雑食」
- 「スズメ目は雌雄同色。例外はニュウナイスズメ」
- 「スズメ目の分布は全国。例外はミヤマガラスで本州西部・四国・九州に生息」
*上記、すべて狩猟鳥獣にのみ限定しています。
なんて具合に鳥獣の分類に注目して共通点を探すのです。で、マガモ属に属するのはどのカモか? スズメ目ってどの鳥? ということはちゃんと暗記する、と。
また「陸ガモ=植物食」「海ガモ=動物食」「夜行性の狩猟鳥獣の中で植物食なのはヌートリアだけ(残りは雑食 or 動物食)」といった、ある特徴から別の特徴を繋げて覚えるのも有効です。
この体系的な知識と次にご紹介する「鳥獣のストーリー」を組み合わせていくと、思ったよりも簡単に覚えられます。
3. 鳥獣のストーリーを想像する。
鳥獣のストーリーと言うと、ちょっと大袈裟なのですが、「ツキノワグマ=雑食」だとか「ハクビシン=夜行性」といった各項目を単純に丸暗記しようとせず、ストーリー立てて理解していく覚えやすいです。
そのために参考になるのは狩猟読本の「鳥獣に関する知識」の章。たとえば――
(ツキノワグマは)木登りが得意で、ブナやミズナラ・ヤマブドウの実などを樹上で採食することも多い
これを「ツキノワグマは木登りが得意」「ツキノワグマは木の実を食べる」とバラバラに覚えるのではなく、「木登りが得意だから、木の上で、木の実を食べるんだ」と動物の特徴として繋げて覚えていくことがポイントだと思います。
この「鳥獣に関する知識」の章を見ると、そのために必要な情報がたくさん書いてあります。ほかにも――
(ハクビシンは)夜行性でかつ樹上生活者であるために人目に触れることは少ない
しかも「たしかに普段見かけることが少ないナァ」という体験とセットで覚えれば忘れにくいものです。
4. 図鑑や実物を見る
試験勉強と、延々参考書をにらめっこしていると辛いもの……。
私は途中から図鑑や実物の写真も見るようにしました。
狩猟読本に出てくる絵はすごく受験者に優しくて、動物の特徴をはっきり捉えて、わかりやすく書いてくれています。最終的にはこの絵を暗記することになるのですが、試しに実物の写真を見てみたり、図鑑の特徴を読んでみたりすると、記憶が多角的に補強されるのか、覚えやすくなる印象がありました。
また、普段の生活でもヒヨドリ、ムクドリ、スズメ、カラス、キジバトなど発見しやすい鳥獣もいるものです。意識して観察すると楽しく勉強できますよ。
わたしはある晩、家の外の木にハクビシンがいるのを発見しました。懐中電灯を当てても逃げないので、光を当てたまま、双眼鏡でジーッと観察を続けたことがあります。
5. 「鳥獣の判別」対策:特徴を言葉で覚える
絵を見て、鳥獣の種類を当てる「鳥獣の判別」の問題ですが、とりあえずは黙々と暗記するしかありません。
しかし、いざ試験となると、絵を見てすぐに答えなくてはならず、「あれ? これってヒドリガモだよな。ホシハジロじゃないよな?」と不安になることも……。
そんなときに大事になるのが「言葉」でした。
人それぞれ覚え方はあると思いますが……
- 「マガモは首が青緑、白い首輪模様、黄色いくちばし」
- 「カルガモは他のカモの雌みたいに茶色、くちばしは黒。先端は黄色」
- 「小ガモは赤い顔、目の周りに緑の帯」
という具合に言葉で特徴を暗記します。で、試験では心の中で「(ワイン色の顔で、首に縦線、しっぽも長いから)オナガガモ!」という具合に自信をもって答えられるというわけです。
おまけ:「鳥獣の判別」に役立つYouTube
鳥獣の判別はこの動画がオススメです
これを見ながら、No.5で書いたような特徴を口にしつつ答えていきます。
これが迷いなく解けるようであれば、概ね問題ないかと……。
これから受験される方へ
きっと狩猟はやりたくてやるのでしょう(害獣駆除として仕方なく、という人もいるでしょうけど……)。
やりたくてやるのだから、試験対策などと思わず、これから自分が獲るかもしれない動物の特徴だと思って、楽しく覚えるといいと思います。
わたしは楽しかったですよ。
また、おもしろいと思ったらこちらをクリックしていただけると、ランキングが上がります。応援のつもりでお願いします。
ブログ村へ