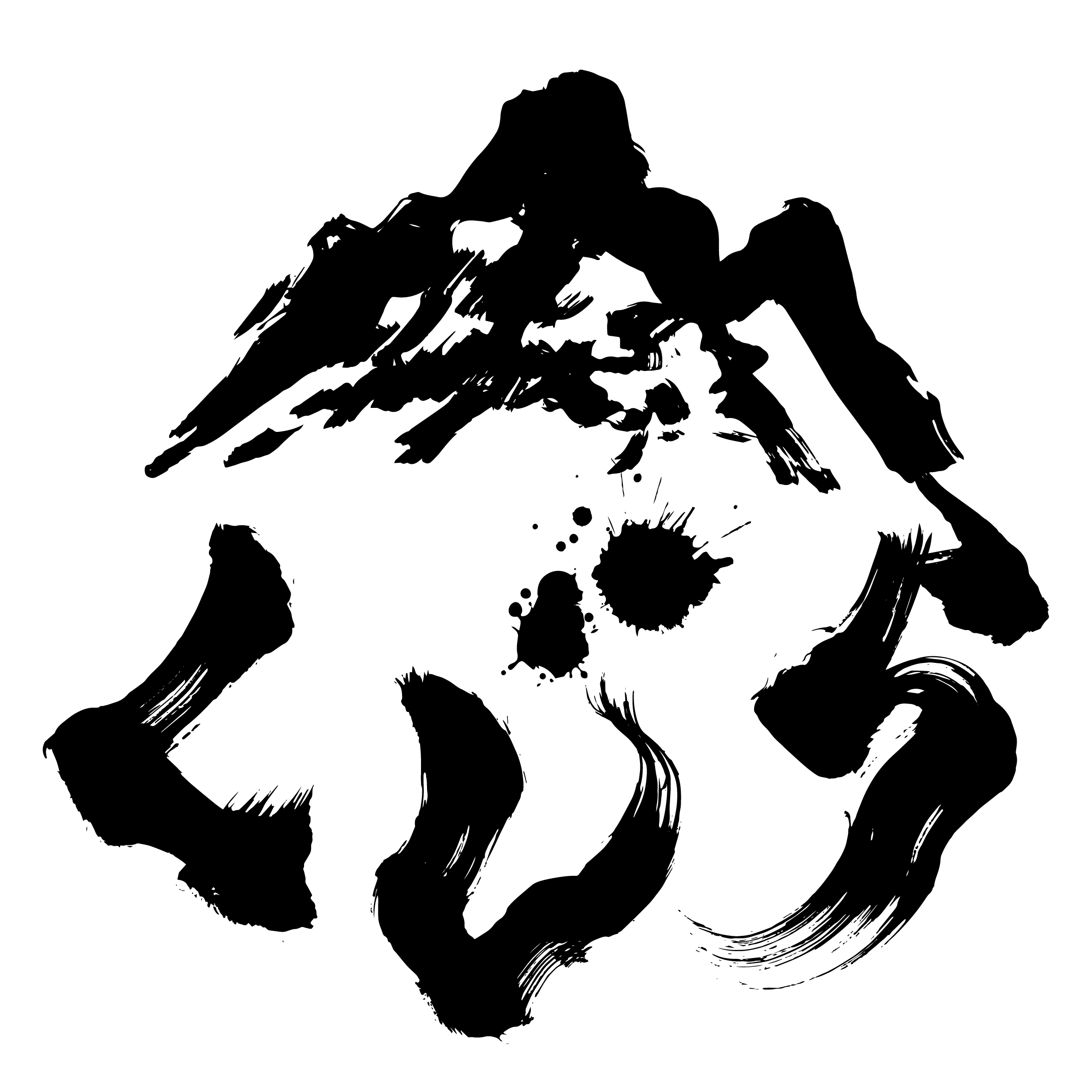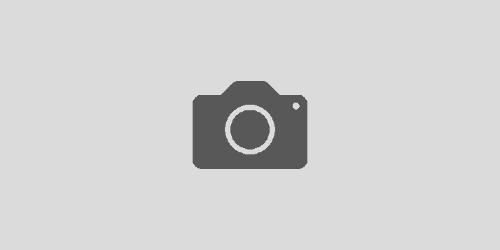書評:山人たちの賦 個人にライトを当て描かれる、リアルな山人の姿
この本を通して著者を想像したとき、「山に飛び込み、泥だらけになりながら話を聞く男」の姿が頭に浮かびました。
山人たちの賦(甲斐崎圭)
この本を手にした大きなきっかけは表紙に「マタギナガサ」がデンッと載っていたからです。しかも撮影用に取り揃えたピカピカのものではなく、いかにも使い古されたナガサだったことが気持ちを惹き付けました。
本の内容は13人の山人のルポルタージュです。マタギはもちろん、職漁師、イワナの養殖師、ボッカ、山小屋の主人など、山に生きる職業人の姿が描かれています。
これが期待以上のおもしろさ、男臭さ、山臭さ、人間臭さに溢れた1冊でした。
そして、この感覚が生まれてくるわけを、エピローグを通して理解しました。
こういう作業(執筆)をやる中で、わたしが自分にかしたのは、お茶を飲んだり酒を飲んだりして話を聞くだけでなく、必ず現場に同行させてもらうということだった。彼らの話の行間から人生を読み取るのではなく、実際の現場に立ち会い、血と汗の中から、涙や笑いを読み取りたかったのである。
この徹底した現場主義がキレイゴトじゃない、生々しい山人の実態を浮き彫りにしたのだろうと思います。
また、こんなことも書いています。
もっと民俗学の世界にまで立ち込んで書いた方がいいのではないかという意見をくださる方もあったが、わたしは意見としては有難く頂きながらも、決して民俗学の立場に立って彼らのドラマを書くことはしなかった。(中略)民俗学では書き切れない彼らの “個人” の山の人生を書くのがわたしの仕事だという気持ちがあったし〜(後略)
「民俗学の世界にまで立ち込んで」という意見があったということですが、わたしはむしろ、著者の現場主義、個人主義の観点こそ、民俗学の原点だと思うのです。
民俗学の分野でわたしが尊敬している川喜田次郎先生(チベットやネパールの民族学で有名)も、徹底して現場や現実を重視します。
学問の名の下に「この地域の人は○○だ」とカテゴライズすると、なんとなく全体像を理解した気にこそなりますが、実際のところ何も理解していないに等しい、とそんなようなことを川喜田次郎先生は仰っていました。むしろ「A氏はこうで、B氏はこう、C氏こうだった」と事実を積み重ねていくことでこそ、本当にその民族のことを理解できる、という考え方です。もし『KJ法』をご存じでしたら、まさにそれです。
とにかく、著者の甲斐崎圭氏は本当にあっちこっちへと行き、この山人たちと(たとえほんのわずかな時間でも)山仕事に同行し、その空気感を肌で理解しようとしているのが、言葉の合間合間から感じ取れます。
これがこの本の魅力です。
30年の重み
13編のルポのうち一番古い『北の山の熊撃ち』や「阿仁のマタギ」は1986年が初出です。
実に30年前。
そして《文庫版附記》として、各章末にこの30年で起きた大きな変化が短く記されています。
誰かが亡くなったり、別の人が仕事を継いだり、ときの重さや紡いでいく時間の流れのようなものを感じます。
山に興味がある人にはおもしろい本だと思います。各章は長くないので、短編好みの人にもお勧めです。
また、おもしろいと思ったらこちらをクリックしていただけると、ランキングが上がります。応援のつもりでお願いします。
ブログ村へ